IT業界で耳にする「キラキラ系エンジニア」。最新技術を追い、SNSやカンファレンスで派手に自己アピールし、「カッコいい」イメージをまとうエンジニアたちだ。彼らはトレンドを牽引する一方、チームでの協調性や実務でのリスクも引き起こす。
この記事では、キラキラ系エンジニアの特徴、背景、現場での問題行動、そしてどう向き合うべきかを、実際の体験談も交えて考察する。エンジニアとして誰もが持つ「特別でありたい」気持ちと、ビジネスの現実の間で、どうバランスを取るべきか考えてみよう。
キラキラ系エンジニアとは?
キラキラ系エンジニアは、以下のような特徴を持つ。
2025年の今、Xで「#エンジニア」タグを見ると、キラキラ系の派手なポストが目立つが、「中身が薄い」との批判もちらほら見られる。
自己ブランディング重視
XやQiitaで最新技術の活用をアピールし、カンファレンスで派手なスライドで登壇。技術力以上に「目立つこと」に注力。
トレンドへの敏感さ
React、AI、Web3など、流行りの技術やライブラリに即飛びつく。公式ドキュメントをなぞった発表やポストで「最先端」を演出。
おしゃれなイメージ
MacBook片手にカフェでコードを書く、スタートアップ的な自由な働き方をアピール。「エンジニアってカッコいい!」を体現。
なぜキラキラ系エンジニアは存在するのか?
キラキラ系が生まれる背景には、業界や社会の構造がある。これらの環境が、技術力以上に「カッコよさ」を追求するキラキラ系を量産している。
エンジニア職の「キラキライメージ」
メディアやSNSで「エンジニア=イノベーションの最前線、高収入、自由な働き方」と持ち上げられる。おしゃれなオフィスや高スペックPCでの仕事が「カッコいい」とされ、若手が憧れる。
SNSとカンファレンスの影響
Xでのバズやカンファレンス登壇は「成功」の象徴。承認欲求を満たす場として、キラキラ系は「最新技術で目立つ」ことを目指す。
採用市場の競争
優秀なエンジニアを求める企業が増え、個人ブランディングが重要に。XやGitHubで「最先端の自分」をアピールすることで、スカウトされやすくなる。
企業の合理的採用戦略
スタートアップやベンチャー企業は、キラキラ系エンジニアを意図的に採用している。彼らの発信力は「最新技術を使うモダンな会社」というブランディング効果を生み、似たような志向のエンジニアを呼び寄せる。結果として応募者の母数が増え、その中から真に優秀な人材を選別できる合理的な戦略となっている。
技術者の本質的欲求
実は、エンジニアなら誰もが潜在的にキラキラ系だと言える。新技術への憧れ、技術的優秀さで認められたい気持ちは技術者の本能。問題は、SNSやカンファレンスという「舞台」がその欲求を表面化・加速させることだ。
キラキラ系エンジニアの特徴
キラキラ系には、以下のような性格的傾向がある。これらの傾向はモチベーションを高める一方、チームでの協調性を損なうリスクをはらむ。
強い承認欲求
「いいね!」やフォロワー数、登壇の拍手など、他者からの評価を強く求める。Xでの「〇〇ライブラリ使ってみた!」ポストは典型。
高いプライド
「俺の選んだ技術が最先端」「古い技術はダサい」と考える。技術マウントを取ることで、自分の「優秀さ」を証明しようとする。
個人主義
チームより自分の成果やイメージを優先。報連相を怠り、独断で技術導入を進めることも。
ビジネス視点の欠如
「技術的にカッコいいか」を最優先し、「ビジネス価値があるか」「ユーザーのニーズに応えるか」「ROIは適切か」といった視点が抜け落ちがち。最新技術を使うこと自体が目的となり、売上向上や問題解決といった本来の目標を見失う。
実際の現場でよくある問題行動
キラキラ系が現場で引き起こす問題は多岐にわたる。
無意味なコード書き換え
動いているコードを「最新ライブラリだから」と理由でリプレイス。ユーザー価値やパフォーマンス向上に繋がらず、バグやメンテコストを増やす。
報連相の欠如
チームの合意なく新技術を導入し、トラブルを招く。Xで「〇〇でフルリプレイス成功!」とポストする裏で、チームが後始末に追われる。
技術マウントによる対立
「その技術、古いよ」と他者を批判し、議論がエゴのぶつかり合いに。チームの雰囲気を悪化させる。
精神的安全性の低下
独断的な行動やマウントが、メンバーの発言を萎縮させる。心理的安全性が損なわれ、協力やアイデア出しが減る。
実体験:キラキラ系エンジニアとの摩擦
キラキラ系の行動がチームに及ぼす影響を、実際のエピソードで振り返る。ある同僚Aさんは、普段から技術話に熱心で、プライベートでもカンファレンス参加やQiita投稿を精力的に行う典型的なキラキラ系だった。仕事にも熱心に見えたが、ある事件が起きた。
私が提出したプルリクエスト(PR)をAさんがレビュー。いくつか改善点を挙げられたが、私がコードの意図と経緯を説明し、改善点を否定する形になった。Aさんは納得いかなかったのか、公式ドキュメントや動作確認で検証を始めたが、結果的に私の主張が正しいと認め、「あなたが正義だった」とコメント。だが、「正義」という言葉に違和感を覚えた。チーム開発は協力して行う物。そこに「正義」や「悪」はあるのか?
その後、Aさんが転職を報告。実は以前から他のチームとも摩擦があり、このPRが引き金になったのか退職に至った。(私の説明の仕方にも問題があったのかしれない…)
問題はここからだ。転職までの残りの勤務期間、Aさんの態度が急変。私の仕事をSlackで監視し、改善提案と称して揚げ足取りや煽り発言を連発。ミーティングでも技術マウントが目立ち、チームの雰囲気が悪化した。
その後Aさんは退職し、彼の真意はわからないが、まるで承認してくれる「キラキラな場」を求めて転職したかのようだった。この経験から、キラキラ系の承認欲求やプライドが、チームの信頼や協力を壊すリスクを痛感した。
彼らと共に働く上での注意点や対策
キラキラ系と上手く働くには、傾向を理解し、リスクを抑える対策が必要だ。
報連相の徹底
技術導入やコード変更はチームの合意とレビューを必須に。独走を防ぐルールを明確化。
目的ドリブンの文化
新技術導入前に「何の課題を解決する?」「ユーザーへの価値は?」を問い、目的を見失わない。
心理的安全性の確保
ミーティングで全員が発言できる環境を整え、技術マウントをリーダーがシャットダウン。「データや根拠で話して」と促す。
地味な仕事の評価
保守やバグ修正、ドキュメント整備も高く評価。「目立つ仕事」ばかり追い求める風潮を抑える。
キラキラ系の強みを活かす
発信力やトレンドキャッチ力は、コミュニティ貢献や新技術検証に役立つ。適切な場面で活躍させ、チームにプラスに。
キラキラ系エンジニアのメリット
キラキラ系エンジニアには確かに問題もあるが、彼らが持つ価値を無視すべきではない。適切に活用すれば、チームや組織にとって大きなメリットをもたらす存在でもある。
発信力と影響力
技術ブログやカンファレンス登壇により、会社の技術力をアピール。個人ブランドが会社の認知度向上に直結する。優秀なエンジニアほど技術情報に敏感なため、こうした発信は採用において強力な武器となる。
技術トレンドの牽引
新技術への敏感さと学習意欲は、組織全体の技術レベル向上に貢献。保守的になりがちなチームに新しい風を吹き込む役割を果たす。
スタートアップ・ベンチャー企業の積極採用
多くのスタートアップやベンチャー企業が、キラキラ系エンジニアを意図的に採用している。これは単なる偶然ではなく、限られたリソースの中で優秀な人材を獲得するための合理的な戦略だ。彼らの持つ発信力と影響力を活用することで、採用競争において大手企業にも対抗できる武器を手に入れることができる。
採用の連鎖効果
一人のキラキラ系エンジニアが発信することで、「この会社は最新技術を使っている」というイメージが広がり、似たような志向の人材が集まる。カンファレンスで自社の技術的取り組みを発表したり、企業の技術ブログで最新技術の導入事例を紹介することで、会社の技術力が外部に可視化される。こうした発信を見た優秀なエンジニアが「この会社なら自分も成長できそう」と感じ、応募につながる。特に転職市場で活発な優秀層にリーチしやすくなる。
採用の母数拡大による選別効果
キラキラに惹かれて応募した中にも実力者は混じっている。面接で技術力・協調性を見極めることで、「発信力もあり実務もできる」理想的な人材を獲得できる。応募者が少なければ選択肢も限られるが、母数が多ければ優秀な人材を見つける確率が高まる。
企業とエンジニアのWin-Winの構造
企業は採用競争力アップと技術ブランド向上を得て、キラキラ系エンジニアは最新技術に触れる機会と発信の場を得る。業界全体としても技術トレンドの牽引と情報共有の活性化につながる。
採用時の見極めポイント
キラキラ系エンジニアを採用する際、メリットを活かしつつリスクを回避するための見極めポイントを紹介する。
技術マウント傾向のチェック
面接で他の技術やフレームワークについて質問した際、「それは古い」「使う意味がない」といった否定的な発言が多い場合は要注意。技術選択の理由を建設的に説明できるかを確認。
ビジネス視点での説明能力
過去の技術選択について「なぜその技術を選んだのか」を、技術的メリットだけでなく、ビジネス価値やユーザーへの影響、コスト面からも説明してもらう。「カッコいいから」「最新だから」だけでは不十分。
チームワークの確認
「チーム内で技術的な意見が割れた時、どう対処したか」「他のメンバーが理解していない技術を導入する際の進め方」などの質問で、協調性や説明能力を評価。
地味な実務への取り組み姿勢
バグ修正、レガシーコードの保守、ドキュメント整備など、目立たない作業についての経験と考え方を聞く。「やりたくない」「つまらない」という回答は、実務でのミスマッチリスクが高い。
発信内容の質的評価
技術ブログやSNSの発信が、単なるトレンド追従ではなく、実際の問題解決や深い理解に基づいているかを確認。表面的な情報の羅列ではなく、実体験や考察が含まれているかがポイント。
まとめ
キラキラ系エンジニアは、技術者が持つ自然な欲求が現代の環境で表面化した現象だ。特別でありたい、尊敬されたいという人間らしい気持ちの表れであり、彼らの発信力やトレンドへの敏感さは、チームや業界に新しい風を吹き込む可能性を持つ。
企業にとっても、キラキラ系の採用は採用戦略として合理性がある。技術ブランディング効果により応募者の母数を増やし、その中から優秀な人材を選別できるからだ。業界全体としても、技術トレンドの牽引と情報共有の活性化に貢献している。
しかし、ITの現場は自己実現の場ではなく、ユーザーやビジネスに価値を提供する場だ。承認欲求やプライドが度を過ぎると、チームの協調性やサービスの安定性を損なう。実体験からも、キラキラ系の個人主義が摩擦や対立を生み、チームの信頼を壊すリスクが明らかだ。
大切なのは、キラキラ系を一方的に批判するのではなく、彼らの傾向を理解し、適切なルールや文化でリスクを管理すること。そして、私たち自身も潜在的なキラキラ系として、「特別でありたい」気持ちに流されず、技術や権威に目を曇らせない冷静さを持つこと。
キラキラ系の強みを活かしつつ、チームワークとユーザー価値を優先するバランスこそが、エンジニアとして、そして組織として成長する鍵なのだ。
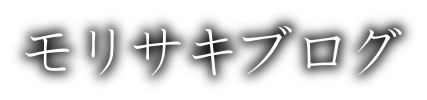



コメント