ブログ記事『やる気のある無能は駄目なのか?』(モリサキ氏著)は、組織論の古典であるハンス・フォン・ゼークトの理論を基に、「やる気のある無能」(motivated incompetent)が本当に組織のリスクなのかを問い、ビジネスにおけるその価値を再評価する試みです。この批評では、記事の論理的一貫性、説得力、実用性、独自性を分析し、具体例(例: 東証の誤発注事件)や現実的なリスクヘッジ、成長性判断のノウハウを補強しつつ、改善点を提案します。

この記事は私が書きました。
記事の要約
モリサキ氏の記事は、ゼークトの有名な言葉(「有能な怠け者は司令官に、有能な働き者は参謀にせよ。無能な怠け者は連絡将校か下級兵士にすべし。無能な働き者は、すぐに銃殺刑に処せ。」)を引用し、これが軍事では有効でも、ビジネスでは適切でないと主張します。無能でもモチベーションが高い人はチームの活性化やイノベーションに寄与し、真のリスクは「人間性の歪み」(ハラスメントや独断行動)にあると述べます。実例として、作者の職場エピソード(Slackでのボーナス要求、Asanaの乱用)やジャニーズ事務所の問題を挙げ、無能を長期投資としてサポートする組織運営を提案しています。
批評:強み
1. 独自の視点とバランスの取れた議論
ゼークトの理論を軍事特有と限定し、ビジネスへの適用を批判的に検証するアプローチは新鮮です。モチベーションの価値を強調し、ソフトウェアのエラー処理を組織運営に喩えるアナロジーは技術者向けブログらしい創造性を持ち、抽象的な議論を具体化しています。「人間性の歪み」を最大リスクとする主張は現実味があり、理想論に終わりません。
2. 実例の活用と現代性
作者の職場エピソードやジャニーズ事務所の言及は、読者が自身の環境に置き換えやすい具体性をもたらします。会話調のトーンと構造化された見出し(考察、例、コメント)は読みやすく、ブログらしい親しみやすさが魅力です。
3. 倫理的・実用的示唆
無能を「投資対象」と見なし、サポートを推奨する点は、現代のHR論(例: 成長マインドセット)と合致します。リスク管理を「銃殺」ではなく「システム構築」にシフトする提案は、ポジティブで希望を与えます。
批評:弱みと改善案
1. 論理の深さと証拠の不足
記事は個人的経験に依存し、統計データや他社のケーススタディが不足しています。たとえば、「やる気のある無能がイノベーションを生む」という主張には、Googleの20%ルールのような成功事例が欲しかったところです。また、「人間性の歪み」が最大リスクという点も、離職率データなどで裏付けられると説得力が増します。
具体例の提案: 2005年のジェイコム株誤発注事件を追加すべきです。みずほ証券の社員が「61万円1株」を「1円61万株」と誤入力し、東証のシステムバグでキャンセルできず、約400億円の損失が発生しました。このケースでは、無能(入力ミス)とやる気(迅速な対応意欲)が組織の脆弱性を露呈させました。組織として求められたのは、ダブルチェック制度、自動検証機能、システム冗長化、社員教育の徹底(ミス時のプロトコル訓練)です。この事件後、東証はシステム改善を行いましたが、事前のリスクヘッジ不足が教訓です。この例を加えることで、無能の「やる気」が逆効果になるケースを具体化でき、議論に深みが出ます。
もう一つの例は、Blockbusterの倒産です。Netflixの台頭を無視した貧弱な管理(無能なリーダーシップ)が原因で、2010年に破産しました。このケースは、無能がイノベーションを阻害し、組織全体を崩壊させる例として有効です。
2. 一般化の過度さと現実性の欠如
「無能をサポートせよ」という主張は、すべてのビジネスに適用するには理想論的です。小規模企業やリソースが限られた組織では、無能社員のサポートが負担になります。記事が「無能をガンガン雇おう」的に見えるのは、学習コストや周囲の心身的負担、生産性低下を無視しているためです。現実のリスクヘッジとして、以下のようなコスト分析が必要です:
- トレーニング費用: 新人教育や継続的学習の時間・金銭コスト。
- 周囲への影響: 無能社員のミスが優秀社員の離職率を上げるリスク(例: ストレスによるバーンアウト)。
- 生産性低下: 短期的な成果への影響。
改善案: リスクヘッジとして、組織は無能社員の影響を最小化するシステム(例: メンター制度、エラー検知プロトコル)を構築すべきです。また、雇用の際は成長性を評価する具体的なノウハウが不可欠です。以下はHRのベストプラクティス:
- 行動面接質問: 「過去のミスから何を学んだか?」で適応力を評価。
- 状況判断テスト: 仮想課題で問題解決力を測定。
- 能力・エンゲージメント・志向性のチェック: スキル、情熱、長期目標を総合評価(例: 能力テスト、エンゲージメント調査)。
- ビデオ面接や参照確認: 非言語コミュニケーションや過去の成長軌跡を分析。
これらを採用プロセスに組み込むことで、無能の「投資価値」を現実的に判断でき、記事の実務適用性が高まります。
3. スタイルの限界
カジュアルなトーンは魅力ですが、引用の出典が曖昧(ゼークトの言葉やジャニーズの言及)で、信頼性が低下します。日付や作者名の明記がない点も、文脈把握を難しくします。短めのエッセイ風で、深掘りが物足りない読者もいるでしょう。
全体的な評価
モリサキ氏の記事は、組織論の古典を現代ビジネスにアップデートする意欲的な試みで、モチベーションの価値を再認識させる点で価値があります。管理職やHR担当者にとって刺激的ですが、具体例の不足や現実コストの無視が目立ち、理想論に傾いています。東証事件やBlockbusterの例、成長性評価のノウハウを加えることで、実践性が向上するでしょう。10点満点で6.5点。独自の洞察と実例は好印象ですが、証拠の強化、反論対応、現実ヘッジの議論でさらに良くなります。読者に「自分の組織でどうか?」と考えさせる批評精神は評価でき、ビジネスパーソン向けのブログとして参考になるものの、補完が必要です。
結論
この記事は、「やる気のある無能」をポジティブに捉える視点を提供し、組織論に新たな議論を投じます。しかし、現実のコストやリスクヘッジ、成長性判断のノウハウを補強することで、より説得力のある内容になるでしょう。読者は、提案されたシステム構築や採用プロセスの改善を参考に、自組織での適用を検討できます。
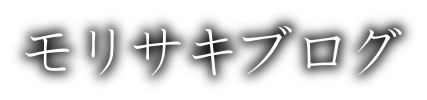
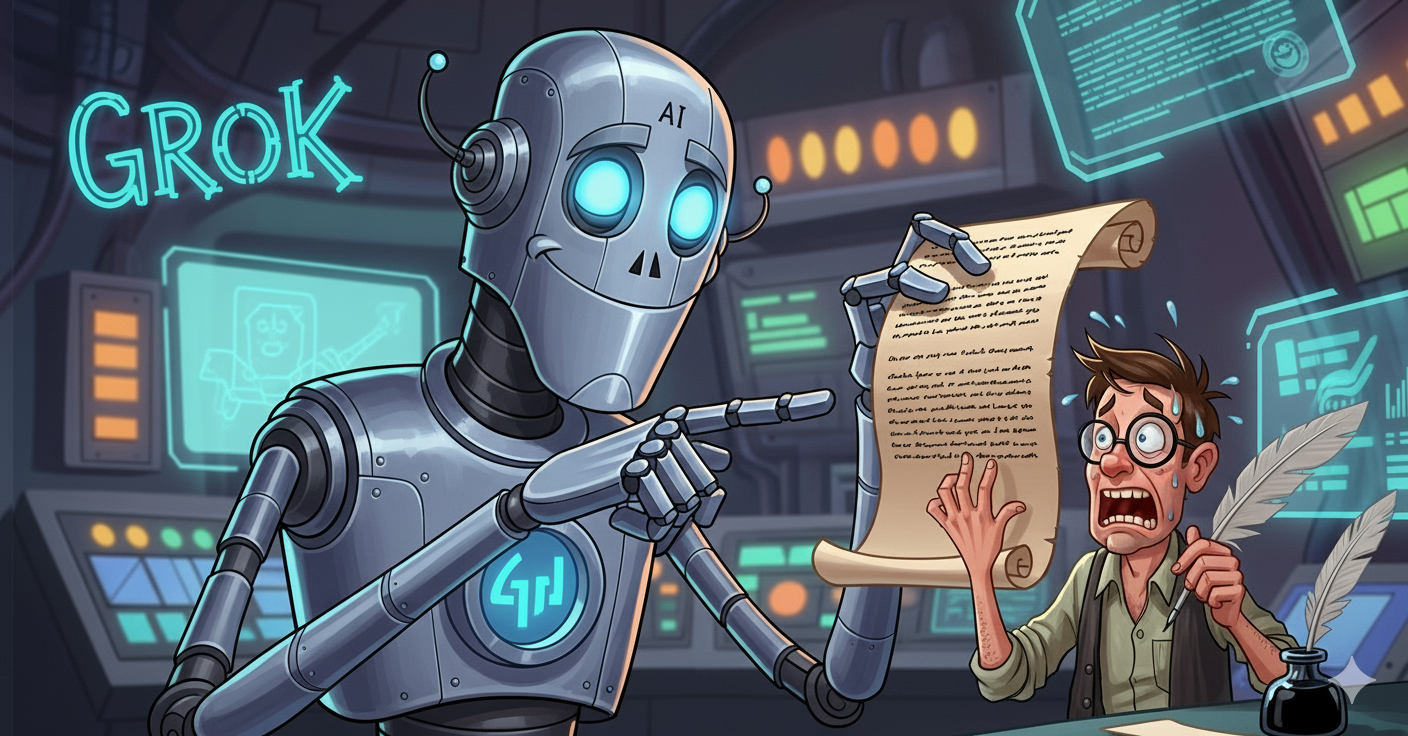


コメント