「来週の全社会議、フリーランスの方も参加お願いします」
「今度のキックオフでビジョン共有するので、ぜひ聞いてください」
こんな誘いを受けたとき、内心「うーん…」と思ったことはありませんか?フリーランスエンジニアとして常駐していると、こうした場面に遭遇することが少なくありません。
別に会社に敵対心があるわけでも、協力する気がないわけでもない。ただ、私たちフリーランスが重視するポイントと、会社側が期待することの間に、微妙なズレがあるのです。
この記事では、フリーランスエンジニアの本音を率直にお伝えしつつ、企業側にとっても有益な人材活用のヒントを提案します。
フリーランスが働き先に求めること
フリーランスエンジニアは会社に対して、効率性と専門性を重視したスタンスで関わります。率直に言えば、会社への深い貢献よりも自分の利害(キャリア、報酬、働きやすさ)を追求しています。
これは冷たく聞こえるかもしれませんが、これこそがプロフェッショナルな関係の本質です。お互いの利益を明確にし、win-winの関係を築く。それが健全なビジネスパートナーシップだと考えています。
私たちは企業のビジョンや長期戦略よりも、自分の技術力を活かせる環境と適正な報酬、そして次のキャリアにつながる経験を最優先で求めています。
技術的な議論は大歓迎、ビジョンは必要最小限
私たちは技術の専門家として参画しています。アーキテクチャの選定、パフォーマンスの改善、セキュリティの強化など、技術的な議論には積極的に参加し、建設的な提案をします。むしろ、そこでの貢献を期待されていると理解しています。
一方で、会社の3年後のビジョンや事業戦略については、直接的な関与は必要ありません。業界調査でも、フリーランスの約7割が「技術的な成果と報酬を最優先する」と回答しています。企業の長期的な発展は経営陣の責任で、私たちは技術面でのプロとして貢献したいのです。
働きやすさが生産性を左右
働きやすい環境は成果に直結します。モダンな開発ツール、効率的なワークフロー、必要最小限のミーティングがあれば、高いパフォーマンスを発揮できます。逆に、古いツールや非効率な慣習があると、本来の技術力を活かしきれません。
フリーランス向け調査でも、働きにくい環境を理由とした短期離脱が約6割に上るとされています。私たちにとって環境の良し悪しは、継続的な協力関係を決める重要な要素です。
報酬と自由度のバランス重視
報酬は技術力に対する正当な対価として重要です。ただし、ストレスが多すぎる環境では、高い報酬よりも働きやすさを優先することがあります。「報酬はいいけど、毎日終電まで無駄な会議」では意味がないと現実的に判断します。
多くのフリーランスが報酬と自由度のバランスを最も重視していることが、各種アンケートからも明らかになっています。
キャリアは戦略的に構築
キャリア戦略は自分のスキルポートフォリオを中心に考えます。新しい技術への挑戦、難易度の高い課題解決、次の案件につながる実績作りなど、技術的な成長に直結する経験を求めます。
会社の研修制度より、実際のプロジェクトでの技術的挑戦を重視します。クライアントとはプロフェッショナルな信頼関係を築ければ十分で、深い組織的なつながりより、お互いの専門性を尊重する関係を好みます。
実際によくある会社の扱い
会社側がフリーランスの特性を理解していないために、ミスマッチが起こりがちです。以下、具体的な例を挙げます。
ジョブ型なのに履歴書を求める矛盾
「技術力重視でジョブ型採用です」と言いながら、職務経歴書だけでなく履歴書の提出も求められることがあります。学歴、職歴の詳細、志望動機まで書かされる場合もあります。
ジョブ型雇用なら「何ができるか」が全てのはずですが、実際は従来のメンバーシップ型採用の慣習から抜け出せていない企業が多いのが現実です。
こうした矛盾した対応が、フリーランス側の「本当に理解されているのか?」という疑念を強くし、双方の信頼関係構築を阻害する要因になっています。
ビジョン共有会への参加要請
準委任契約でシステム開発を担当しているのに、全社のキックオフやビジョン共有会に「ぜひ参加を」と誘われることがあります。「会社の方向性を理解してもらいたい」という気持ちはわかりますが、私たちにとっては技術的なタスクに集中したい時間です。
そもそも、フリーランスとの契約は1〜3ヶ月程度の短期でリスクヘッジしているはずなのに、なぜ長期的なビジョン共有が必要なのでしょうか?このような契約をしておきながら、正社員と同じような会社への帰属意識を求めるのは矛盾していると思います。
参加を控えめにお断りしても、特に業務に支障は出ませんでした。むしろ、その時間を技術調査に使った方が、プロジェクトに貢献できたと感じます。
退出時の競業避止・守秘義務の過剰要求
準委任契約終了時に「同業他社への転職禁止」「会社批判の禁止」といった誓約書への署名を求められることがあります。
これは準委任契約の本質を完全に理解していない典型例です。短期契約でリスクヘッジしておきながら、退出時には正社員以上の拘束を求めるのは完全に矛盾しています。フリーランスは複数のクライアントとの契約で生計を立てており、競業避止を課すなら正社員として雇用し、相応の保障をするべきです。
もちろん、こうした過剰な要求は拒否して構いません。準委任契約において、通常の守秘義務を超える拘束条項への署名義務はありません。毅然とした対応をとることで、適切な契約関係を維持できます。
正社員転換の提案
「優秀な方なので正社員になりませんか?安定しますよ」とスカウトされることもあります。お気持ちは嬉しいのですが、「自由な働き方を求めてフリーランスを選んだ」ことをご理解いただけていないと感じます。
組織的な巻き込み
親睦会や歓送迎会への誘いは、普通に嬉しく参加させていただきます。ただ、組織運営に関わる会議や、チームビルディングを目的とした長時間の研修などは、プロフェッショナルな関係で十分と考えています。
なぜそんな扱いをするのか?
会社がこうした対応をする背景には、理解不足があります。悪意があるわけではないのですが、以下のような要因が考えられます。
正社員中心の組織運営
長年正社員中心で運営している会社は、フリーランスも同様に扱いがちです。人事制度や会議体が正社員前提で設計されているため、技術専門職としての役割を意識せず、組織の一員として同じルールを適用してしまいます。
フリーランスの価値観への理解不足
フリーランスが技術的な成果と効率性を重視する価値観を知らないため、組織一体感の醸成を重視してしまいます。ビジョン共有や深い関与を求められても、私たちは専門技術での貢献を望んでいます。
一体感への過度な期待
会社が「全員で一丸となって」と考え、ビジョン共有や組織的なイベントを重要視します。これは正社員のモチベーション向上には効果的ですが、フリーランスにとっては技術的な課題に集中したい時間を削られる結果になります。
人材不足という現実的な背景
ここまで理想論を語ってきましたが、企業側が正社員転換を急いだり、環境整備が後回しになったり、フリーランスにも正社員と同じような関わりを求めてしまう背景には、深刻な人材不足があることを理解しています。
優秀なエンジニアの確保は企業にとって死活問題です。良いフリーランスを見つけたら「なんとしても手放したくない」と考えるのは自然な反応で、だからこそフリーランスの価値観を十分に理解する前に正社員転換を提案してしまったり、組織の一員として深く関わってもらおうとしてしまいます。
長年正社員中心で運営してきた組織が、突然ジョブ型の人材活用に切り替えるのも簡単ではありません。制度や文化の変更には時間がかかり、現場の管理者も手探り状態なのが実情です。
正社員とフリーランスの適材適所
企業が効果的に人材を活用するには、正社員とフリーランスの特性を理解した使い分けが重要です。
これは単なる個人の好みや性格の違いではなく、ジョブ型とメンバーシップ型という根本的な雇用観の違いです。フリーランスは「明確な職務に対する対価」を求めるジョブ型雇用、正社員は「組織の一員としての帰属」を前提とするメンバーシップ型雇用として機能します。
この違いを理解せずに、ジョブ型で働くフリーランスにメンバーシップ型の文化(ビジョン共有、組織一体感)を求めると、双方にとって非効率な結果を招きます。
正社員の特性と活用法(メンバーシップ型)
- 長期的な成長投資:時間をかけた育成、キャリア開発支援
- 組織への愛着醸成:ビジョン共有、企業文化への深い参画
- 継続的な関係構築:チームビルディング、組織運営への関与
フリーランスの特性と活用法(ジョブ型)
- 即戦力として活用:現在の技術力で即座に成果を期待
- 専門性の集中投入:明確な技術課題での専門性発揮
- 外部視点の導入:新しい技術や手法の積極的な提案
この違いを理解せず、フリーランスに正社員と同じ扱いをすると、双方にとって非効率になります。フリーランスは「技術特化型プロフェッショナル」として、専門性を最大限活用する方が高い成果を生みます。
会社にとっても非効率
ニーズを無視した扱いは会社にとっても損失です。以下、理由を説明します。
フリーランスの離脱リスク
技術に集中したい私たちが、関係性の薄い会議や組織的なイベントに時間を割かれると、ストレスが溜まります。「もっと技術に集中できる現場を探そう」と考え、エージェントに相談することになります。
業界データでも「役割の理解不足による早期離脱」が約4割に上るとされています。優秀な技術者が流出し、プロジェクトの品質と進行に影響が出ます。
成果の低下と人材確保の困難
技術的なタスクを妨げられると、本来の専門性を発揮できず、納期や品質に影響が出ます。会社が私たちの合理的なニーズを無視すると、win-winの関係が築けません。結果として、次回以降の優秀なフリーランス確保が困難になります。
改善案
会社側がフリーランスの特性を理解すれば、双方にメリットが生まれます。以下、具体的な改善策を提案します。
契約と役割の明確化
契約書で技術的なタスク範囲を明確に定義し、組織運営への関与は最小限に抑えます。報酬体系は成果連動型やマイルストーン方式を採用し、プロフェッショナルな関係を維持します。技術的な挑戦や新しいスキル習得につながるタスクを優先的に割り当てることで、双方のメリットを最大化できます。
環境とツールの整備
技術的な議論の場は積極的に設け、ビジョン共有系の会議は任意参加とします。開発環境には現代的なツール(Docker、Kubernetes、GitHub Actions、Slack、Notion、Figmaなど)を導入し、レガシーなツールや慣習を見直します。
特にタスク管理では、RedmineやExcelベースの管理、古いバージョンのJira、メールでのタスク依頼などは効率性を大幅に下げます。GitHubのIssueやNotionを使っている現場とRedmineでチケット管理をしている現場では、同じフリーランスでも作業効率とモチベーションが全く異なります。
業界調査でも「開発環境の最適化が生産性を30%向上させる」とされており、投資対効果は十分に見込めます。
しかし、こうした理想的な環境整備は、スタートアップや小規模企業など、資金やリソースに制約がある場合、すぐに実現するのが難しいかもしれません。
重要なのは、ツールそのものよりも「なぜ」その環境なのかを正直に伝えることです。
多くのフリーランスエンジニアは、企業の状況をある程度理解しています。そのため、「現時点では予算の都合で理想的な環境は整えられないが、将来的にこう改善していく計画だ」と正直に伝えることで、かえって信頼関係が生まれます。
コミュニケーションの最適化
オンボーディング時に技術的なバックグラウンドと関心領域をヒアリングし、専門性を活かせる領域での議論を重視します。定期的な技術的成果のフィードバックを行い、プロフェッショナルな関係を維持します。
組織的な親睦は適度に保ちつつ、過度なチームビルディングは避ける配慮が効果的です。
人材活用の長期視点
フリーランス向けの運用ガイドラインを整備し、社内で「技術特化型人材」としての適切な活用方法を共有します。技術的な貢献度を正当に評価する仕組みを導入し、継続的な協力関係を築く基盤を作ります。
正社員転換を成功させるコツ
正社員としてフリーランスを誘いたい気持ちはよく理解できます。優秀な技術者を手放したくないのは当然ですし、実際に成功している例も多くあります。ただし、アプローチ方法を工夫すれば成功率は大幅に向上します。
「安定」ではなく「技術的挑戦」をアピール
「正社員になれば安定します」ではなく、「新しいアーキテクチャにチャレンジできます」「技術選定の裁量権があります」「チームリードとして技術的な意思決定に関わってもらいたい」といった、スキルアップと裁量権をアピールしましょう。
私たちは安定よりも、技術的な成長と挑戦を求めています。
信頼関係を先に構築
いきなり正社員転換を提案するのではなく、まず半年から1年程度、理想的なフリーランス扱いで信頼関係を築くことが重要です。お互いの価値観と働き方を理解してからの提案の方が、受け入れられやすくなります。
技術的な議論での相互尊重、適切な裁量権の付与、成果に対する正当な評価などを通じて、「この会社となら正社員でも良いかも」と思ってもらえる関係を作りましょう。
総合的な条件提示
年収だけでなく、技術環境、開発の裁量権、働き方の自由度、技術的な挑戦の機会を含めた総合的な条件を提示しましょう。私たちが重視するポイントを理解した包括的な提案が効果的です。
また、「試用期間」として数ヶ月間の正社員体験期間を設けることで、双方のリスクを軽減できます。
まとめ
フリーランスエンジニアは技術的な専門性と効率性を重視し、プロフェッショナルな関係を好みます。私たちは技術の議論には積極的に参加し、建設的な提案をしますが、組織のビジョンや長期戦略への深い関与は求めていません。
これは決して協力的でないということではなく、それが本来の専門職としての役割分担だと考えています。
企業側が正社員とフリーランスの特性を理解し、それぞれに適した活用をすることで、双方の成果が最大化されます。技術的な議論を重視し、組織的な巻き込みは最小限に抑える。この使い分けができれば、優秀な技術者との継続的な協力関係が築けるはずです。
私たちフリーランスは、専門技術を活かして企業の成果に貢献したいと考えています。適材適所の人材活用で、より良い協働関係を築いていきましょう。
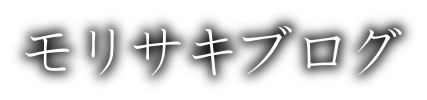



コメント