「年収1000万円になったら法人化すべき?」
この疑問に対する答えは、年収1000万円なら絶対に個人事業主のままです。
多くのサイトで「年収1000万円が法人化の目安」と書かれていますが、これは大きな間違いです。個人事業主が使える節税制度を正しく理解すれば、年収1000万円レベルでは個人の方が圧倒的に有利だからです。
この記事では、年収別に個人事業主vs法人化の最適解を、税金・手間・将来性を含めて徹底検証します。
⚠️ 必ずお読みください
- この記事の計算は概算であり、実際の税額は個人の状況により大きく異なります
- 法人化の判断は必ず税理士に具体的なシミュレーションを依頼してください
- 最新の税制改正により計算が変わる可能性があります
- 扶養家族の有無、事業内容、経費の種類等により最適解は変わります
- この記事の内容による損失について、当サイトは一切の責任を負いません
最終的な判断は必ず税務の専門家にご相談の上で行ってください。
前提条件の設定
共通設定
計算の前提条件
- 経費率:20%
- 単身者、扶養家族なし
- 東京都在住
- 2024年度税制で計算
年収と所得の関係
各年収レベルでの所得
- 年収1000万円 → 所得800万円
- 年収2000万円 → 所得1600万円
- 年収1億円 → 所得8000万円
年収1000万円:個人事業主が圧勝
年収1000万円レベルでは、個人事業主の節税制度をフル活用することで、法人化を大きく上回る手取りを確保できます。
個人事業主(節税制度フル活用)
基本の税金計算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得税 | 153.6万円 |
| 住民税 | 80万円 |
| 個人事業税 | 24万円 |
| 国民健康保険 | 70万円 |
| 国民年金 | 19.9万円 |
| 税金・保険料合計 | 347.5万円 |
個人事業主最強の節税制度
| 制度 | 年間上限 | 節税効果(税率33%) |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 84万円 | 27.7万円 |
| iDeCo | 81.6万円 | 26.9万円 |
| 合計節税効果 | 165.6万円拠出 | 54.6万円 |
実質手取り:652.5万円 + 54.6万円 = 707.1万円
将来受取時の税制優遇
個人事業主の節税制度は積み立て時だけでなく、受け取り時も大幅な優遇があります。
小規模企業共済の優遇
- 退職所得控除で大部分が非課税
- 一時金受取なら20年で1600万円まで税金ゼロ
iDeCoの優遇
- 年金受給控除または退職所得控除
- 受取方法の選択で税負担を最小化
20年積立後の資産:約3300万円(運用益含む)
法人化の場合(役員報酬600万円設定)
法人側の計算
- 利益:800万円 – 600万円 = 200万円
- 法人税等:約50万円
- 法人手残り:150万円
個人側の計算
- 役員報酬:600万円
- 給与所得控除後:426万円
- 各種税金・保険料:148.7万円
- 個人手残り:451.3万円
合計手取り:601.3万円
法人化のメリットを考慮しても
追加メリット
- 消費税2年猶予:年100万円(2年限定)
- 経費拡大効果:年30万円程度
- 維持費用:▲年35万円
実質的な年間メリット:95万円(最初の2年のみ)
年収1000万円の結論
個人事業主の方が年間100万円以上有利
選択理由
- 税制優遇:個人の節税制度が強力すぎる
- 将来資産:3300万円の資産形成が可能
- 手間なし:複雑な手続き不要
- 柔軟性:廃業や規模縮小も簡単
年収1000万円なら迷わず個人事業主を選ぶべきです。
年収2000万円:法人化検討ライン
年収2000万円(所得1600万円)になると、税率の差が効いてきて、状況が変わり始めます。
個人事業主(節税制度フル活用)
基本の税金計算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得税 | 372万円 |
| 住民税 | 160万円 |
| 個人事業税 | 65.5万円 |
| 国民健康保険 | 85万円 |
| 国民年金 | 19.9万円 |
| 税金・保険料合計 | 702.4万円 |
節税効果を加味した手取り
- 小規模企業共済+iDeCo:165.6万円拠出
- 節税効果:約75万円(税率45%で計算)
- 実質手取り:897.6万円 + 75万円 = 972.6万円
法人化(役員報酬900万円設定)
法人側の計算
- 利益:1600万円 – 900万円 = 700万円
- 法人税等:約175万円(実効税率25%)
- 法人手残り:525万円
個人側の計算
- 役員報酬:900万円(給与所得控除後705万円)
- 税金・保険料:約190万円
- 個人手取り:710万円
合計手取り:1235万円
法人化の追加メリット
消費税対策
- 2年で400万円の猶予効果
- 資金繰りの大幅改善
経費拡大の威力
- 役員社宅:家賃の50-80%を経費化
- 出張費・日当の活用
- 年間50万円程度の節税効果
退職金準備
- 法人の利益を退職金原資に
- 将来的に大幅な節税効果
年収2000万円の結論
3年スパンで見ると法人化が約300万円有利
法人化の条件
- 3年以上継続する見込みがある
- 事務負担増を受け入れられる
- 税理士報酬年30万円は必要経費と割り切れる
個人事業主の節税制度も強力ですが、年収2000万円レベルでは税率の差(45% vs 25%)と消費税猶予効果により、法人化にメリットが出始めます。
年収1億円:法人化必須レベル
年収1億円(所得8000万円)では、もはや法人化以外の選択肢はありません。個人事業主では税負担が重すぎます。
個人事業主の税金地獄
恐ろしい税負担の実態
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得税 | 3590万円 |
| 住民税 | 800万円 |
| 個人事業税 | 395万円 |
| 国民健康保険 | 100万円 |
| 国民年金 | 19.9万円 |
| 税金・保険料合計 | 4904.9万円 |
節税制度を活用しても
- 小規模企業共済+iDeCoの節税効果:約90万円
- 手取り:約5085万円
- 実質税負担率:49%の地獄
法人化(役員報酬900万円+退職金準備)
法人側の圧倒的優位性
- 利益:8000万円 – 900万円 = 7100万円
- 法人税等:1775万円(実効税率25%)
- 法人手残り:5325万円
個人側の計算
- 役員報酬900万円の手取り:約710万円
合計手取り:6035万円
退職金戦略の威力
法人資金の出口戦略
- 法人蓄積5325万円を将来の退職金に
- 20年後の退職金4000万円程度まで大幅優遇
- 実質税負担率を20%程度まで圧縮可能
年収1億円の結論
法人化により年間約950万円の節税効果
この年収レベルでは議論の余地はありません。法人化は必須です。
マイクロ法人戦略
年収500-800万円の個人事業主には、マイクロ法人という選択肢があります。
マイクロ法人とは
最小限の役員報酬(月6-8万円)で法人を設立し、社会保険料を削減する戦略です。
社会保険料の削減効果
個人事業主(年収600万円)の場合
- 国民健康保険:約45万円
- 国民年金:19.9万円
- 合計:64.9万円
マイクロ法人(役員報酬年84万円)の場合
- 厚生年金:約15万円
- 健康保険:約8万円
- 法人維持費:約30万円
- 合計:53万円
年間約12万円の削減効果
マイクロ法人の注意点
リスクと課題
- 税務署からの指摘リスクあり
- 事務負担は確実に増加
- 将来の年金受給額は減少
向いている人
- 年収が安定している
- 社会保険料負担を軽減したい
- 事務手続きを厭わない
まとめ:年収別最適解
年収1000万円以下
個人事業主+小規模企業共済+iDeCo
法人化を考える必要はありません。個人事業主の節税制度をフル活用すれば十分です。
年収1000-1500万円
個人事業主がまだ有利
ただし、将来的な成長や消費税対策を考えて、法人化を検討し始めるタイミングです。
年収1500-2000万円
法人化のメリットが出始める
3年以上継続する見込みがあれば、法人化を真剣に検討すべきレベルです。
年収2000万円以上
法人化を強く推奨
税率の差が決定的になり、法人化のメリットが明確になります。
年収5000万円以上
法人化必須
個人事業主では税負担が重すぎて、事業継続が困難になります。
よくある間違いと正しい判断
間違った情報:「年収1000万円で法人化すべき」
多くのサイトでこう書かれていますが、完全に間違いです。個人事業主の節税制度を無視した計算に基づいています。
正しい判断基準
税金面での真の損益分岐点
- 年収1500-2000万円が真の分岐点
- 小規模企業共済・iDeCoを考慮した計算が必須
総合的な判断要素
- 事業の継続性(3年以上の見込み)
- 成長性(将来的な売上拡大予定)
- 事務負担への耐性
- 社会的信用の必要性
最重要ポイント
年収だけで決めるな
法人化は年収だけでなく、事業の性質、将来性、個人の価値観を総合的に考慮して判断すべきです。単純な損益計算だけでは見えない要素が多くあります。
結論:年収1000万円なら個人事業主で小規模企業共済とiDeCoをフル活用せよ。法人化はまだ早い。
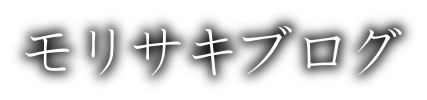



コメント